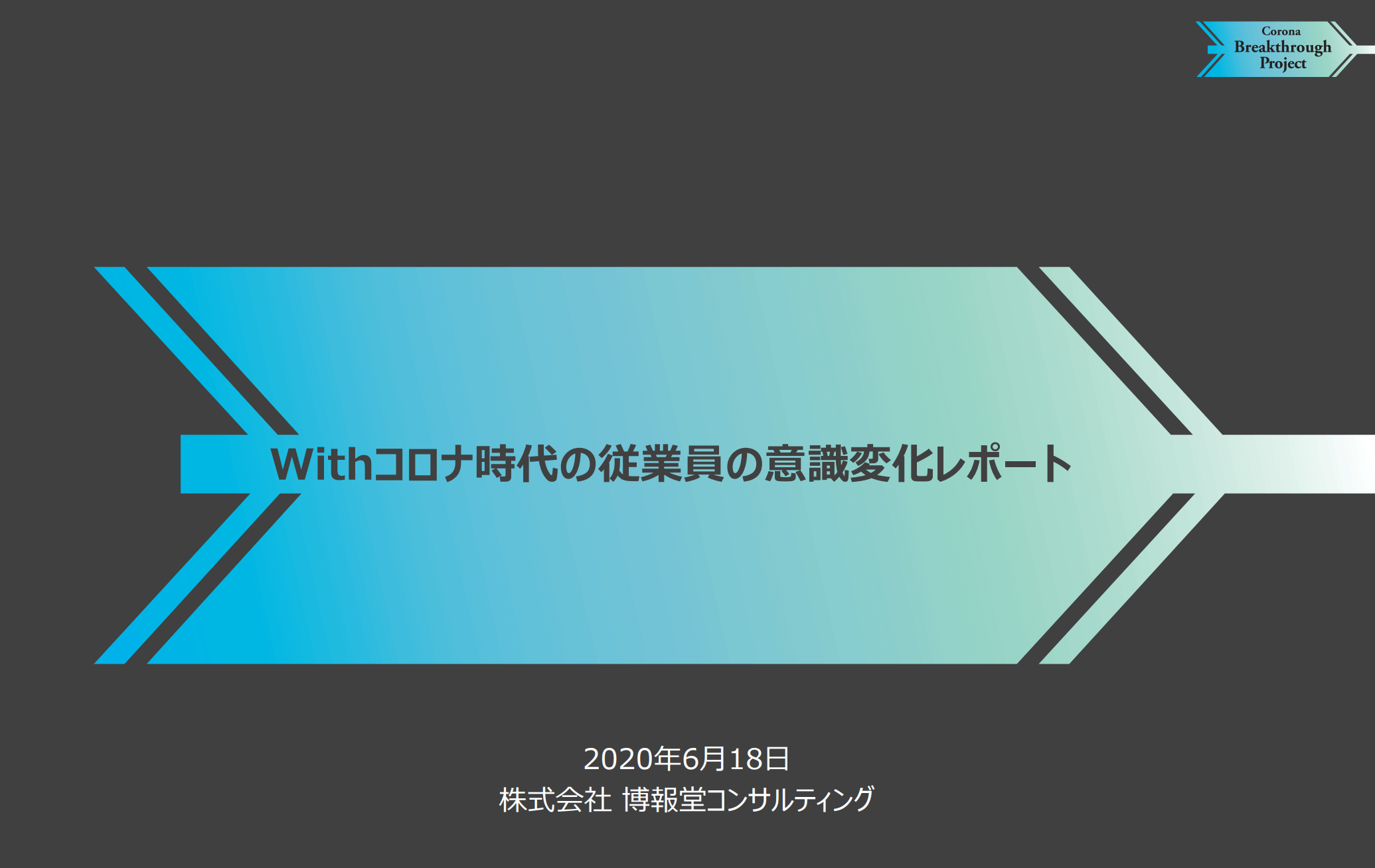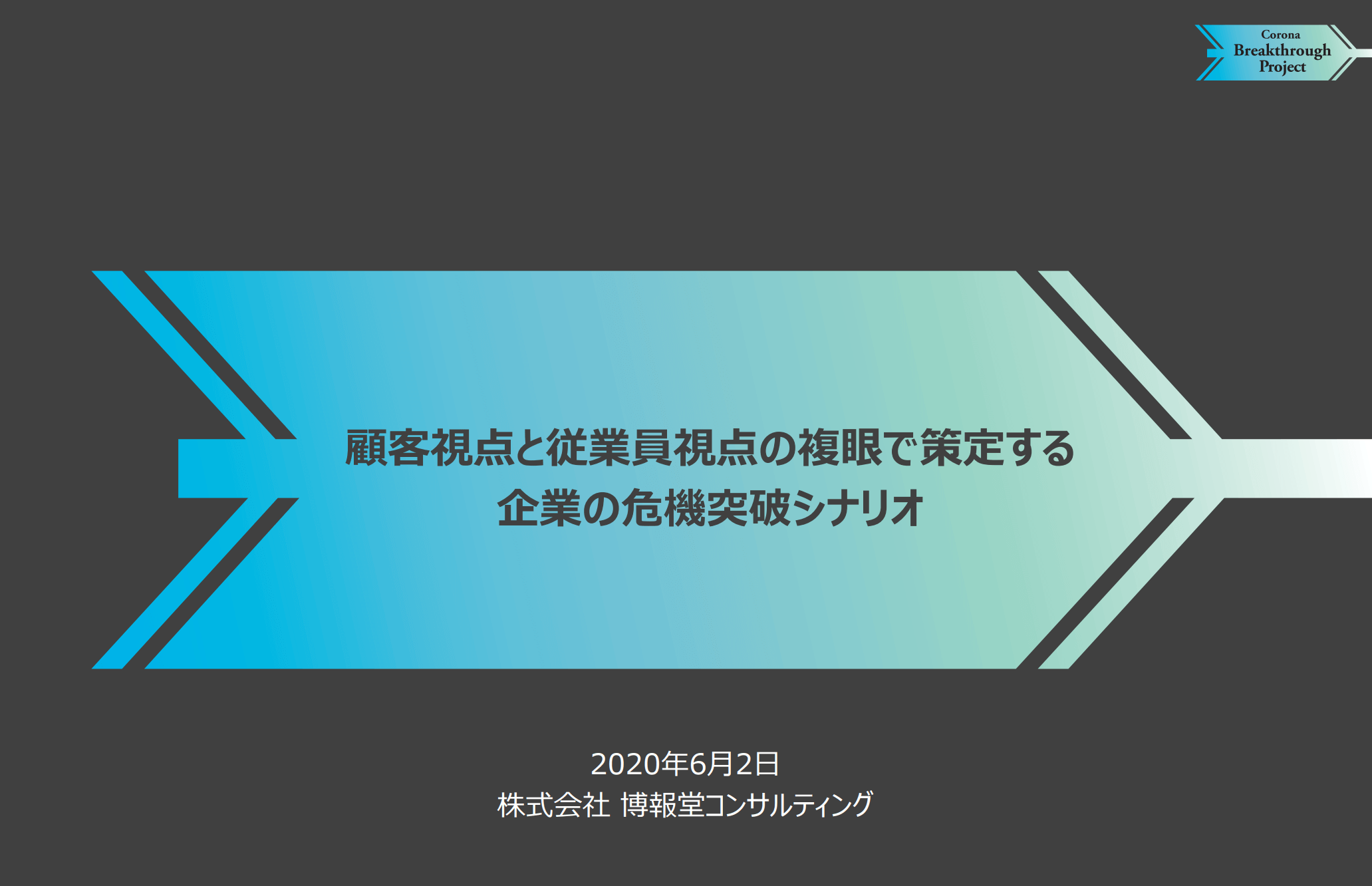日本における「破壊的イノベーション」の概念と理論の普及に寄与された、関西学院大学 専門職大学院 経営戦略研究科 玉田俊平太教授のインタビュー連載最終回です。(以下敬称略/全4回)
第3回 イノベーションを生み出すために必要なこと
(1) 「破壊的イノベーション」を生み出すアイディアをどう見つけるか?
楠本: 破壊的なイノベーションのアイディアは新しい革袋にとのお話がありましたが、そもそもそのようなイノベーションアイディアはどのように見つければいいのでしょう?
玉田: 人事の面接に似ているのですが、いくつかのアイディアをレジュメみたいな身上書にまとめたら、それに対してチェックリストで評価をするのがいいでしょう。そのためのチェック項目がいくつかあるのですが、例えば目指している市場はA大市場、B中市場、Cニッチ市場のいずれかだとしたら、普通の採点基準だと大市場が10点で、中ぐらいだと5点、ニッチだと0点となるかと思うのですが、クリステンセン教授流チェックリストは逆です。大市場だと0点、中市場では5点、ニッチ市場だと10点。
他には、ライバル企業がその製品をどう見るか。Aうちも対抗したいと思うか、B注意深く見守りたいと思うか、Cそこには進出しないもしくは馬鹿にしているのか。この質問でも、答えがAなら0点、Bなら5点、Cなら10点です。
得てして持続的アイディアというのは、大きな市場をターゲットにしがちです。例えば通信白書で「IT市場が30兆円規模になります」と言うと、日本中の企業がみんなIT市場を目指します。ですが、そうするとライバル企業がどんどん参入して来て、血で血を洗う総力戦が始まってしまいます。全くお薦めできません。クリステンセン先生は、だから、ライバル企業がそっぽを向くか、もしくは馬鹿にして全然入ってこないような市場を目指すべきだということで、3番目の選択肢が10点の配点なんです。
逆に、ライバルが喜んで参入してきそうなアイディアは0点なんですね。例えば皆さんの会社で、アイディアの稟議などを通す時に、「競合の状況は?A社とB社も製品化を考えている?よし、じゃあ我が社も参入して頑張ろう」と横並びで判断するケースがあるかと思うのですが、それは逆だと思うんです。もしA社とB社が既に参入を考えていたら、ウチはやめようと言うべきなんです。レッド・オーシャンの中で互いに殺し合いをするより、どこか自由なブルー・オーシャンに行って、1人でその市場を占有して、そこでトップランナーになった方がはるかにいいわけですよね。
そういった非常に直感に反する採点基準で採点し、90点満点であなたのアイディアはどのぐらい破壊的かを判定するという評価法を彼は提案しています。
さらに具体的な評価項目と評価基準は私の近著「日本のイノベーションのジレンマ 破壊的イノベーターになるための7つのステップ」の中でご紹介していますので、実務で新しいイノベーションを起こしたいという方にはお薦めです。
楠本: ニッチ市場を狙おう、ライバル企業がやらないようなことをやろうということはわかるのですが、ただ小さい市場で本当にそれが成長していくかどうか判断がつかない中では、企業はなかなか踏み出すことができないかと思うのですが。
玉田: ですから、このチェックリストの中には、「5年後には大市場になりそうか?」という項目もあります。ずっとニッチのままでは、やはり企業としては、特にマネージャーの視点からするとあまり望ましくないことですので。
それから、「必要とする資本が他社より少ないか?」とか、「より早く市場に浸透出来そうか?」といった評価項目も入っています。
例えば、ウーバー(Uber)というドライバー配車サービスがあります。タクシーを使っていたユーザーからすると、スマのアプリで呼べばすぐ配車してくれて、ドライバーの名前やレーティングも判り、どこまで来ているかがスマホのマップに表示されるので待たされ感も少なく、やって来た車の車内は清潔で、ドライバーとのお金のやり取りやチップは一切なく、すべてクレジットカード決済で、経路地図付き領収書もメールで送られてくるという明朗会計の画期的なサービスです。
そのため、タクシーを使う側からすると、顧客満足が向上するので持続的イノベーションなのですが、既存のタクシー会社も確実に破壊しつつあります。なぜなら、ウーバーは“持たない経営”を徹底しており、それによって既存のタクシー会社にはまねの出来ない“低コスト構造”と“スケーラビリティ”を持っているからです。タクシー会社と異なり、ウーバーは車を保有しません。車を持って時間をもてあましているドライバーと、車での移動を必要としている顧客とをIT技術を駆使して結びつけるサービスだからです(車が清潔なのも、ドライバーが車の持ち主であることも一因でしょう)。車を所有しないからこそ、2009年に米国サンフランシスコで創業した当初はわずか10人だった契約ドライバーが、7年後の現在は100万人を突破し、世界58か国・地域の300都市でサービスを展開して、総走行距離は24億キロメートル(地球と木星の往復に相当)を超え、一説には5兆円もの企業価値があると見込まれるほどのとてつもない急成長を遂げることができたのだと思います。
自動車版のAir B&Bという感じで、車を所有するのはドライバー、車庫を確保するのもドライバー、従ってそういったコストは全くかからない。ドライバーになりたい人は履歴書を送ると、過去の犯罪履歴や運転履歴などをチェックされた上で、パスするとウ―バーのステッカーと、ドライバー向けのアプリが入ったiPhoneが送られてくる。そして自分の好きな時間に、そのドライバー用アプリのボタンをポンと押すと、その時からあなたはウ―バードライバーという仕組みです。これだと企業は車を購入する必要も車庫を確保する必要もなく、ビジネスを拡大するための投資や時間がすごく少なくて済みますね。
クラウドサービスで課金決済や配車などができるソフトを開発し、ドライバー用とユーザー用のアプリを開発すれば、あとはどこにでもあるiPhoneにアプリを入れて、審査したドライバーに配るだけ。コンピューター資源も、自社で持つ必要はなく、必要に応じてクラウドサービスを利用すれば、スケーラブルですよね。そうやって他地域にも展開すればいい訳です。
ですからウーバーは、圧倒的に低コストでスケーラブルなビジネスモデルとそれを実現するソフトウェアがコアなんです。そして、他社よりも早く、あらゆる都市でサービスを提供できるようにすれば、一度ウーバーのアプリにクレジットカード情報を登録したユーザーは、ライバル企業のサービスではなく、次もウーバーを利用しようということになるんですね。
ウーバーのもう一つの画期的な点は、レーティングシステムです。ウーバーを呼ぼうとすると、前回利用したドライバーをユーザーが5段階で評価する画面が出てきます。それをしないと次の車を呼べないというユーザーによるドライバーのレーティングが必須のシステムになっているのです。聞くところでは、5段階評価で平均が4.6以下のドライバーはシステムから外されて仕事が来なくなるとのことです。4.6ですよ、高いですよね。私、授業評価で4.6なんてなかなか取れないです。
このシステムのさらにすごいところは、実はドライバーもユーザーのことを評価しているという点です。以前ウーバーを利用した際その話になり、「あなたの評価は4.9、とても高いです」と言われて、喜んでいいのかどうか微妙な気持ちになったのですが、ドライバー側にもユーザーを選ぶ権利があるので、例えば暴言を吐いたり床を汚したりするようなユーザーはレーティングが低くなるのです。そして、ドライバーは評価の低い人からの呼び出しはパスすることも可能なんです。たとえば「レーティングが2.9と低いユーザーがこの場所で呼んでいますがどうですか?」とドライバー用アプリから聞かれても、無視していると別のドライバーへその客は回され、またそのドライバーもスキップしたらずっと車が来ない。良貨が悪貨を駆逐するシステムが、ドライバー側とユーザー側と両方に入っているんです。まるで経済学の教科書に出てきそうな、とても画期的なシステムだと思います。
このように、資本をあまり必要としないウーバーのようなビジネスの方が、多くの資本を必要とするタクシーのビジネスよりは、よりスケーラブルで早く成長出来ますよね。少ない資本で早く成長できるかどうか、ということがビジネスモデルを評価するうえでは大事だと思います。
楠本: そういったスケーラビリティがあるかどうかが一つの判断基準になるということですね。
玉田: そうですね。リアルな店舗を展開する、例えば居酒屋チェーンを全国に1,000店展開するといった場合、必ずコストも時間もかかります。そういうビジネスよりは、ウ―バーのようなビジネス、あるいはフランチャイズもそれに近いかと思いますが、本人に投資負担をしてもらって、ノウハウを提供することでフィーをもらうというビジネスなどが望ましいですね。
楠本: その段階では市場がなかったとしても、拡大する必然性があるものであればいいと。
玉田: はい、比較的低いコストで早く成長できるアイディアがより望ましいということです。
例えばiPhoneも世界中に普及していますが、Appleが全て生産しているわけじゃなく、EMSを行う会社が工場を建て、従業員教育も含め、製造・納品を請け負う。その会社をAppleが徹底的にクオリティコントロールしているわけですよね。Appleがなぜ4割近い利益率を誇っているのかといえば、製造面を外部委託することで資本効率を高めていることが大きな理由の一つだと思います。

(2) イノベーションを生み出すために必要な「ビジョナリー」
楠本: 生活者の価値観は急には変わらない一方、ライフスタイルはこの10年、20年の中で大きく変わってきています。何が最も影響しているのかというと、テクノロジーなのではないかという人が周りに多く、今後イノベーションを生み出していくために、特にテクノロジーを持たない会社は、テクノロジーをどう見極め、向き合っていけばいいのかと議論をしていたのですが答えは出ませんでした。
玉田: まずテクノロジーの重要性ということですが、おそらく大昔の火の発見まで遡っても、人類が地球上でここまで増え、かつその多くは衣食に困らず、暑くもなく寒くもない空調の効いた家に住み、誰もが世界中の人たちとコミュニケーションを取ることができるというのは、かなりの程度テクノロジーのおかげですよね。そういう意味で、テクノロジーが人口増大や、あるいは富の増大の要因のかなりの部分を占めているというのは事実でしょう。
一つひとつのテクノロジーの深掘りというのは専門家に任せていればいいと思うのですが、経営者などの技術の専門家以外の方も「ビジョナリー」であることが大切だと思います。英語で「ビジョナリー(Visionary)」とは、「未来はこうあるべきという独自の考えを持った人」とのことを表します。つまり普通の人の視力が1.0だとすると、2.0の視力を持った、遠い先の未来までくっきり見える人が「ビジョナリー」です。
例えば、ソニー(当時の東京通信工業)が開発したトランジスタラジオ。当時トランジスタ特許のライセンサーだったウェスタン・エレクトリック社ですら、「トランジスタはとても素晴らしいデバイスだが、まだ耳に聞こえる音声周波数ぐらいしか増幅できない。だからぜひ補聴器を作るべきだ」とアドバイスしたらしいんです。ところがライセンシーである東京通信工業側は、「いや、補聴器というのはマーケットが限られる。でもラジオを作れば、一家に1台どころか、一人1台売れたっておかしくない」と。つまり当時娯楽の主流だったラジオの市場はとても大きいので、トランジスタの性能を向上させ、歩留まりを上げてコストを下げたら必ず売れる、やるべきだと、創業者の井深さん達には「見えていた」のです。そして、その掲げられた高い目標に向かい、技術スタッフであった岩間さん達が、様々な苦難を乗り越え、ついに電池で動くポータブル・トランジスタラジオの開発に成功し、世界中で販売されるようになったわけです。
つまり、「人と違った未来がくっきり見えていた」井深さん、盛田さんという方がいて、トランジスタラジオというイノベーションが実現したのです。技術のディテールではなく、本質的な価値を理解し、その社会的インパクトを構想する柔らかい頭を持ちましょうということなんです。できれば理科系の知識もあるに越したことはないですが、それだけではなく、幅広い視野とセンス、将来に対する鋭い嗅覚を持つことが大切なのです。
そういう意味で、今一番注目すべきは、人工知能だと思います。ディープラーニングとかシンギュラリティといった言葉が飛び交っていて、東大を目指す偏差値60の人工知能や、アメリカのクイズ番組で優勝する人工知能などがすでに実現していますが、そういう技術や性能の観点ではなく、「人工知能が実現しつつある世界で、他社と差別化を図るためには何が必要か」と考えることが重要です。実は、その鍵となるのが「データ」なんです。どうやって、どんなデータを集めて、それを他社より速く人工知能に流し込んで学習させるかが肝になっていくでしょう。言わば、20世紀の前半はハードウェアの時代、後半はソフトウェアの時代でした。そして、21世紀はデータの時代になると思います。つまり、「データを制する企業が世界を制す」ということです。
楠本: 技術の深掘り自体はエンジニアに任せて、技術をどう使うかを考えることが重要なんですね。そして、それは「ビジョナリー」でないとヒットしないと。
玉田: はい。一番難しいのは、社会が今後何を求めるのか、つまり、今後社会が“困ること”は何か、そしてその際に“雇われる”べき技術にはどんな特性が求められるのか、といった市場と技術の両方に対する洞察力が必要だと思います。今後は、“機械に雇われる人”と“人工知能を使いこなして常人の何万倍ものパワーを得る人”の両極端になるおそれがあります。最後は、技術を使いこなし、かつ、将来が見通せる人、そういう人が生き残ると思いますね。
楠本: 一人ひとりのビジネスマンが心掛けてやっていかないと、企業内でも個人でもイノベーションはなかなか生まれないということですね。
玉田: そうですね。
(3) マネジメント知識の半減期は10年
楠本: そのためには、まず明日から何をやればいいのでしょう?
玉田: 今は、知識の陳腐化がどんどん速まっています。「イノベーションの経営学」という教科書の中に、すごく怖いメッセージがあります。「マネジメント知識の半減期は10年だ」と書いてあるんです。半減期10年ってどういうことかというと、10年経つとせっかく学んだ知識の半分が使えなくなる、無価値になってしまうということなんですね。すると、20年経つとせっかく勉強した知識の価値が4分の1になってしまうわけです。だから、20年前のことを言ってもあまり価値がないわけです。それに対抗するには、知識が古くなるよりも速いスピードで新しい知識をインプットし続けるしかないんです。
“Life-long Learning Commitment(生涯学び続ける覚悟)”という表現があるのですが、仕事に疲れて家に帰ってビール飲んでナイター観るだけではなく、例えばたまにはTEDを観るとか、別の知的気晴らしでもいいので、一生学び続けないと、知識社会では無価値になっちゃうんだという自覚をを持って頂きたいなと思います。
幸いなことに、今は学ぶ機会はいくらでもあります。例えばiTunes Uという、iPhoneやiPodを持っている方なら誰でもアクセスできるアプリ。そこでは、ハーバード大学の統計学の授業が全部観られます!
要するに、やる気さえあれば、ただでハーバード大学の授業が受けられる時代なんです。そういうものを利用するのもいいし、どこかに行って縛り付けられないとなかなか勉強しないという方は、ぜひ関学ビジネススクールに来ていただいて…というオチになりますが。
>第4回に続く

関西学院大学 専門職大学院 経営戦略研究科 副研究科長 教授
玉田 俊平太氏
関西学院大学経営戦略研究科副研究科長。博士(学術)(東京大学)。ハーバード大学大学院にてマイケル・ポーター教授のゼミに所属、競争力と戦略との関係について研究するとともに、クレイトン・クリステンセン教授からイノベーションのマネジメントについて指導を受ける。筑波大学専任講師、経済産業研究所フェローを経て現職。
その間、東京大学先端科学技術研究センター客員研究員、東京大学先端経済工学研究センター客員研究員、文部科学省科学技術政策研究所客員研究官を兼ねる。
研究・イノベーション学会評議員。日本経済学会、日本知財学会、International J. A. Schumpeter Society会員。平成23年度TEPIA知的財産学術奨励賞「TEPIA会長大賞」受賞。
2015年9月に「日本のイノベーションのジレンマ〜破壊的イノベーターになるための7つのステップ」を刊行。その他の著書に『産学連携イノベーション―日本特許データによる実証分析』(関西学院大学出版会、2010年)、『巨大企業に勝つ5つの法則』(日本経済新聞出版社、2010年)、『イノベーション論入門』(中央経済社、2015年)、『イノベーション政策の科学:SBIR政策の評価と未来産業の創造』(東京大学出版会 、2015年)、監訳に『イノベーションへの解』(翔泳社、2003年)、『イノベーションのジレンマ』(翔泳社、2000年)、監修書に『破壊的イノベーション』(中央経済社、2013年)、『マンガと図解でわかる クリステンセン教授に学ぶ「イノベーション」の授業』(翔泳社、2014年)などがある。