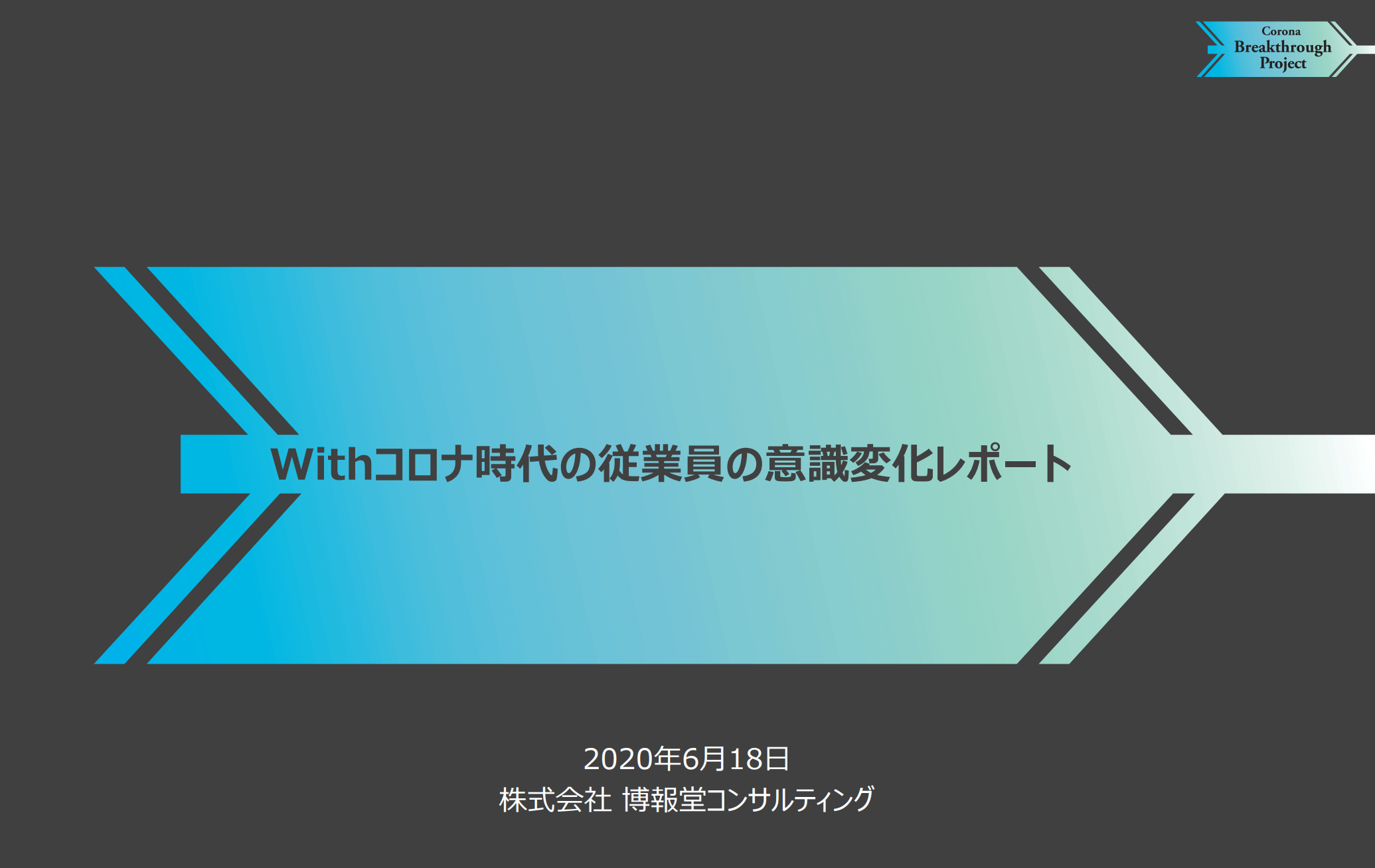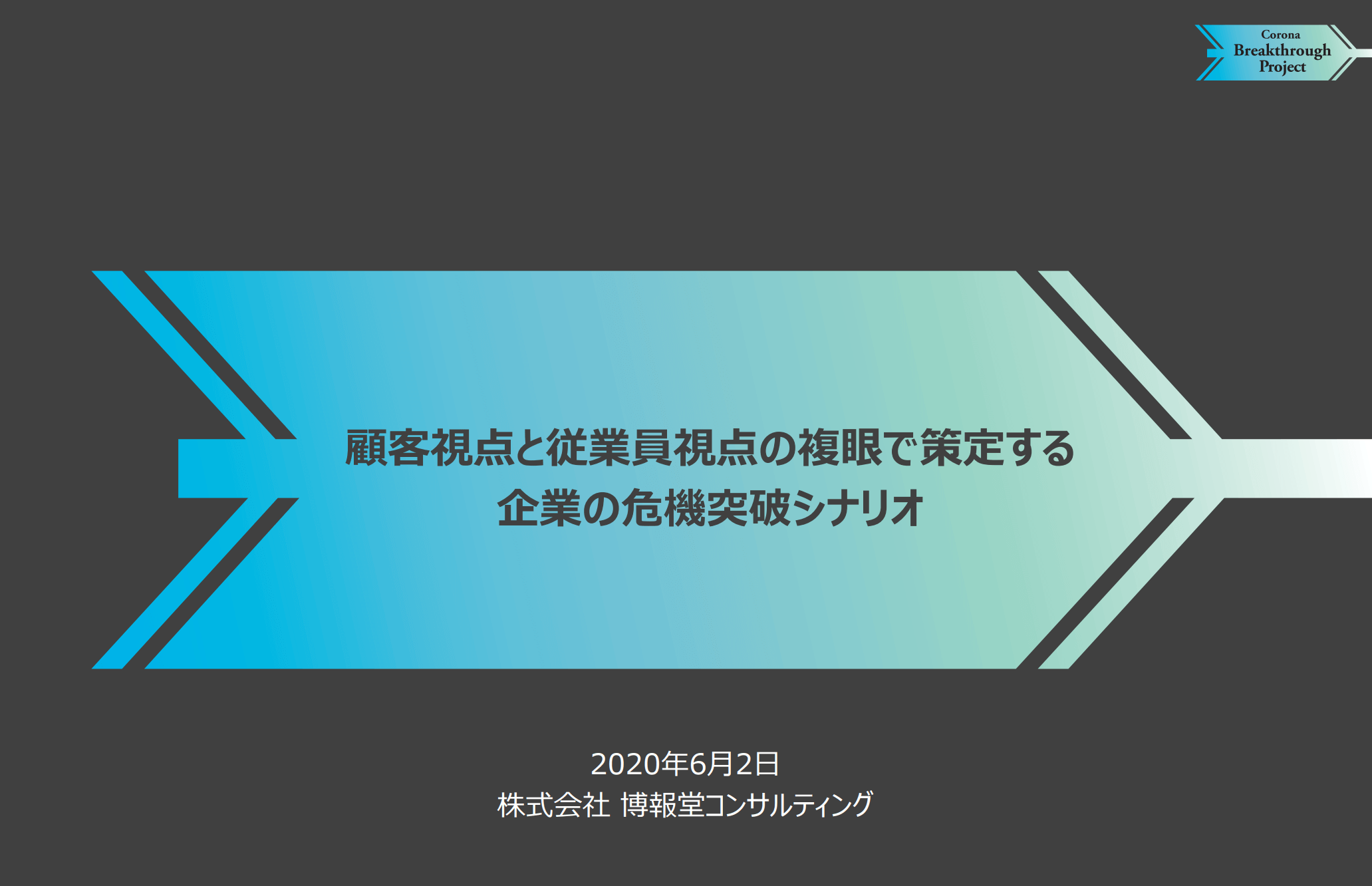世界は再び、イノベーション志向へ
フランス南部のコートダジュール沿いの都市カンヌで毎年5月に開催される『カンヌ国際映画祭』。そのカンヌ国際映画祭の1ヶ月後に、同じカンヌの地、同じ会場で、「カンヌ・ライオンズ (Cannes Lions International Festival of Creativity) 」なるものが行われている。広告業界における世界最大級の祭典として、かつては単なる広告作品としてのクリエイティビティを賞賛するものであった。だが近年、マーケティング・コミュニケーションがカバーする範囲が拡張したことで、フィルム以外の部門も毎年のように次々と新設され、現在では20部門以上にもなる。
さらに最近では、グローバルブランド企業のCEOやCMOが自身の問題意識や最先端事例を共有するセミナーも増え、アワードと肩を並べる程のコンテンツになってきており、さながらビジネス・カンファレンスのようである。

ライオンズ・イノベーション 2015
筆者もマーケティング/ブランディングのコンサルタントとして、グローバルの最先端事例のシャワーを浴びるべく、定期的にカンヌ・ライオンズに参加しているのだが、そのカンヌ・ライオンズで昨年、イノベーション部門がスピンアウトし、「ライオンズ・イノベーション」として独立したアワードとなった。その前年にあたる2014年にはヘルスケア部門が先んじてスピンアウトしたのだが、今後のヘルスケアマーケットにおける世界的な注目度と同様に、イノベーションという分野においても今後ドラスティックに動いていくことが予兆される出来事であった。
その大きな動きのひとつとして筆者が注目したのが、イノベーションを共創する新たな形ともいえる「コ・イノベーション」である。
これまで“イノベーションの共創”というと、協業・提携、M&Aといった企業間コラボレーション、CVCに代表されるベンチャーキャピタル的投資、オープンイノベーションの文脈で語られる生活者参加型の企画・商品開発といった手法が取り上げられてきたが、ここでいう「コ・イノベーション」とは、企業が外部イノベーターとの有機的な関係性によって、イノベーターを社内に取り込む形で実現していく新規事業イノベーションである。
では「外部イノベーターとの有機的な関係性」とは何か。
「Purpose」を起点とする新たなイノベーション共創
昨年のカンヌ・ライオンズにおいて、あらゆるグローバルブランド企業のCEO・CMOが、企業としての社会的存在意義に立ち戻って何をすべきかを考えることこそが21世紀の企業成長の源泉であり、顧客をファンにする唯一の方法であるという文脈において、「Purpose」というフレーズを頻繁に使用していた。
例えば、Volvoは欧米の自転車事故が多いという社会的イシューに対して、車のランプに反射する特殊なスプレー塗料を開発し、自転車ユーザーの衣服や自転車に吹きかけることで自転車事故の撲滅を訴えた。これはVolvoの経営方針である、安全で事故のない自動車ライフを提供するという自社のPurpose(目的、存在意義)に沿って実施した結果であり、カンヌでも先進的事例として多くの賞を獲得した。
これらの背景として、マイケル・ポーターが提唱したCSV(Creating Social Value)の流れから、ソーシャルグッドの重要性が明らかに増しており、いわゆる理論としての経営戦略論から、リアルビジネスにおける必要条件として位置づけが変わってきていることが考えられる。

グローバルブランド企業のセミナーで頻繁に使用される「Purpose」
有機的な関係性に話を戻すと、この企業としてのPurposeを共有できる関係性こそが、イノベーション・パートナーとしての条件であり、そうしたイノベーターを企業が積極的に取り込んでいくという流れが出てきているのだ。
ユニリーバでは、ユニリーバが目指す「持続可能な成長・社会構築」に向けて、同じように社会問題に対して熱烈な関心を持つイノベーターに対し、支援プログラム(The Unilever Foundry)を実践している。
ここで重要なのは、ユニリーバがイノベーターを支援する基準は、ビジネスとしての成長性や自社のプロフィットよりも、“Purposeの共有”を第一義に考えていることである。
ユニリーバはこのイノベーター支援プログラムの中で、「UPWORTHY(アップワーシー)」という社会的に重要なイシューだけを扱うキュレーションメディアを支援しているのだが、月間5,000万ユニークユーザーにも及ぶUPWORTHY上でユニリーバが行っているCSV活動情報も発信されており、持続可能な成長・社会構築をPurposeに据えるユニリーバにとっては、イノベーターを支援することで、自社への共感獲得を促すメディア媒体の獲得に成功しているのである。
このように技術面や資本面での提携や協業といった関係性を超えて、“Purpose”を起点にした新たなイノベーション共創の形が今後ますます拡がってくることが想定される中においては、まず自社の社会的存在意義について、いま一度問い直す姿勢が求められるだろう。
※本コラムは、スルガ銀行グループ 一般財団法人企業経営研究所(http://www.srgi.or.jp/)発行の季刊誌『企業経営 2016年夏季号』(No.135)に掲載された連載「最近のビジネス・コンシューマートレンド」の内容を転載しております。