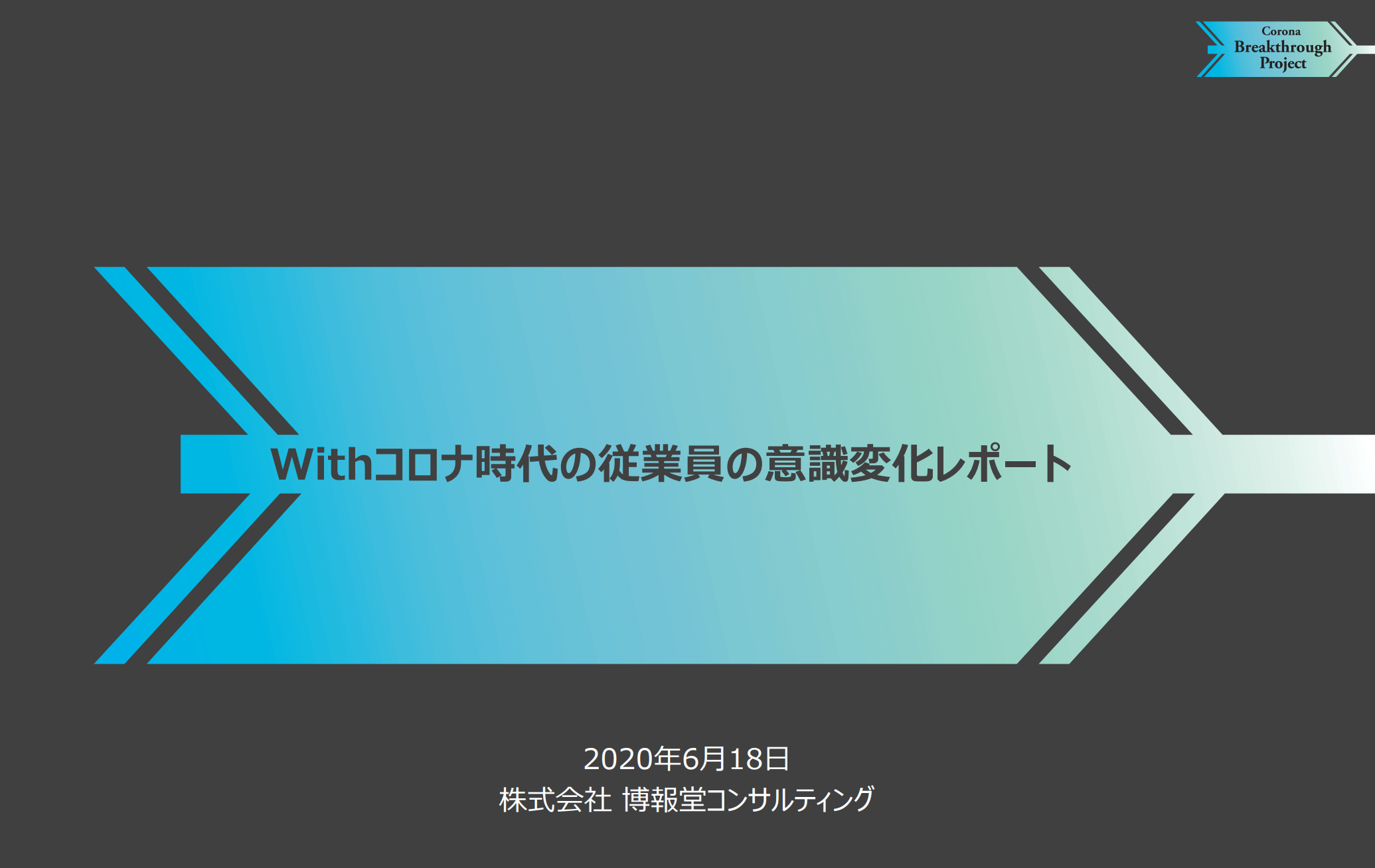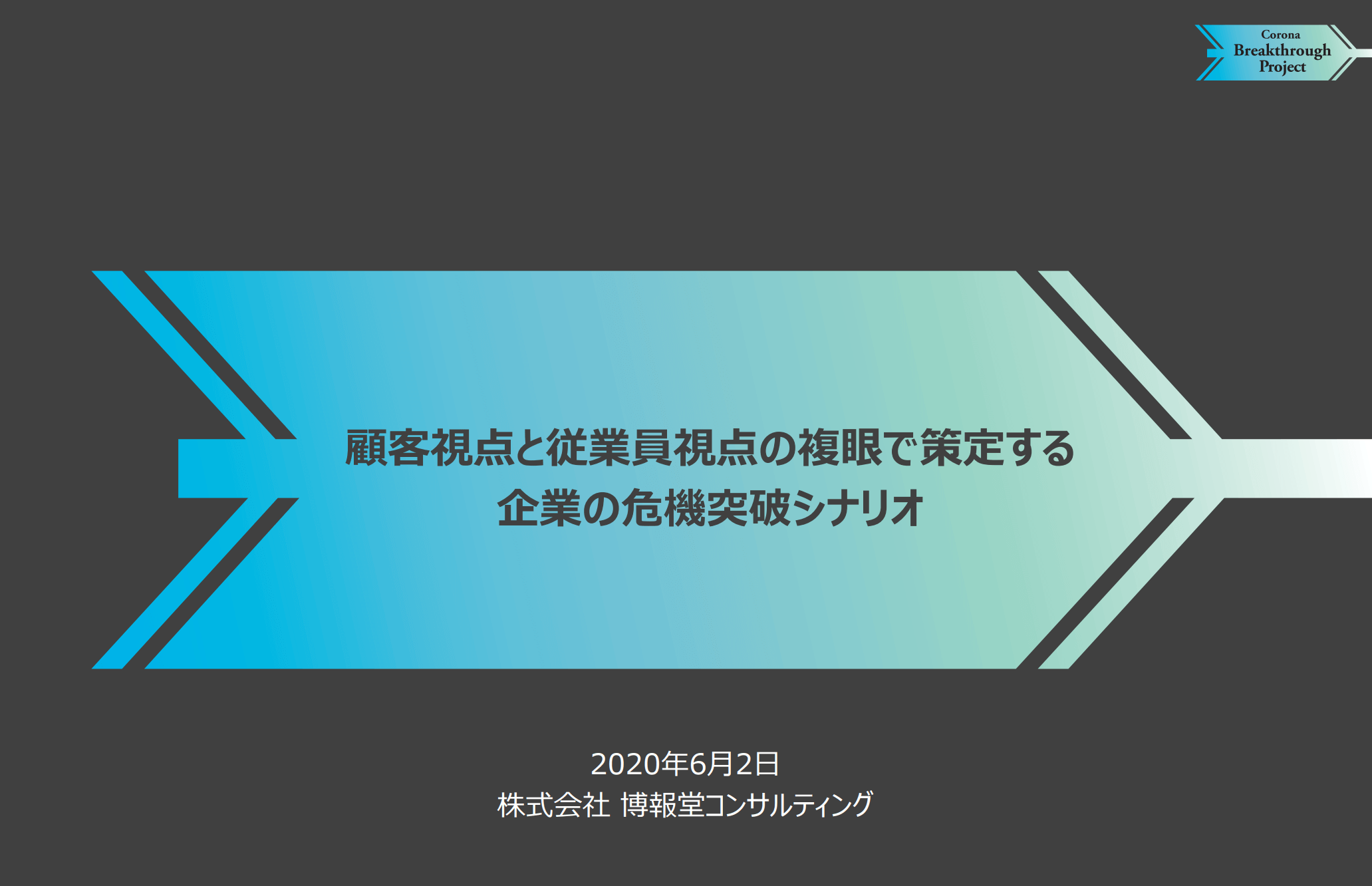企業経営をテーマに、様々なスペシャリストにインタビューをするシリーズです。第2弾は、日本における「破壊的イノベーション」の概念と理論の普及に寄与された、関西学院大学 専門職大学院 経営戦略研究科の玉田俊平太教授です。(以下敬称略/全4回)
第1回 「イノベーション」との出会い
(1) ハーバード大学大学院で「イノベーション」を学ぶ
玉田: 大学を卒業して就職先を考える際に、2つの軸から検討しました。収入が高い・低いという軸と、自分がやりたい・やりたくないという2軸です。
人生の意味ってなんだろう、と考えますと、お金は儲かるけど、それが特定のクライアントに奉仕したことに対する報酬である弁護士やインベストメントバンカーなどのお仕事は、たとえ何億という年収がもらえたとしても、私には、世の中に与えるインパクト、もう少しきれいな言葉で言えば、世のため人のためになっている度合いがそれほど大きくないように思えました。
それに、“起きて半畳寝て一畳”という諺があるように、私は、何事も「足るを知る」ことが大事という考えを持っています。例えばジョージ・イーストマン(コダック創業者)のように、全米有数の資産を得、部屋が37もあり、広大な庭園や果樹園、農場などに囲まれた豪邸に住んでいたとしても、生涯独身で友人も少ない孤独な老後を過ごし、最後は病苦で自殺してしまっては、残念ながら幸せとは言えないように思います。
そこで私は、そこそこ食べられて、且つ“人の役に立つ”仕事がしたいなと思い、国家公務員試験を受けました。公務員は、英語ではパブリック・サーバント(人々への奉仕者)と言われます。まさに、世のため人のために働く、やり甲斐のある仕事だと思いました。
ただ、実際に通産省(当時)に入ってみると、入りたての新人に、「明日までに産学連携を促進する政策を考えろ!」とか言われるわけです。そんなこと言われても、まだ知識もなければ、それを組み立てる理論もない。だから働けば働くほど、知識や理論に対する飢餓感がものすごく高まってきました。
しかし、当時の通産省は“通常残業省”と呼ばれるほどのブラック企業で、終電で帰った日には、なんだか早引けをしたような申し訳ない気分になるほど烈悪な勤務環境でした。私の妻の最大のミッションは、明け方に帰宅して泥のように眠っている私をたたき起こし、どうにか飯を食わせて、遅れないようにドアから送り出すことでした。何しろ、入省を希望する大学生に配布する“先輩の話”のタイトルに「暗いうちに帰りたい」というのがあったほどですから……。
当然、自分で本を読んで勉強する時間など、ほとんどありませんでした。そんなとき、上司の奨めでアメリカの大学院に留学制度で行かせていただけることになり、ハーバード大学の大学院に入りました。
産業政策を考えるためには、やはり産業界のことを知らなければいけないのですが、会社勤めの経験がありませんでしたので、競争力って何?とか、技術と競争力ってどう関係しているの?といった疑問が頭の中で渦巻いていました。そんなときにちょうど、ハーバードビジネススクールで、マイケル・ポーター教授が4年ぶりにゼミ生を募集していたので、願書を出したんです。ポーター先生の授業は人気科目だったので、それを受けるのにはセレクションがあり、履歴書や志望動機といった願書が求められたんですね。1995年頃だったのですが、当時は日本経済もまだ勢いがあって、産業政策など何か謎めいたことをやっていそうな日本の通産省からの留学生は、他のゼミにとっても有意義だろうと思われて入れてもらえたんだと思います。
ポーター教授から、競争力や戦略とはどういうものなのかという基礎理論を教わり、その後、まだ無名だったクリステンセン准教授の「マネージング・イノベーション」という講義を受けました。後で知ったのですが、先生は当時40代半ばぐらいで、ドクターコースを出たばかりの新米教員でした。私は先生の最初期の生徒の一人となったのです。
クリステンセン先生は、ブリガムヤング大学経済学部を首席で出られた後、ハーバード・ビジネス・スクールでMBAを取得し、ボストン・コンサルティング・グループを経て、MITの教授たちとベンチャー企業を創業されました。その後、一念発起して40代でドクターコースに入り直されたんですね。
そのベンチャー時代の実体験から、ハイテクなものが必ずしも市場に受け入れられるとは限らない、それは何故なのか?という疑問をお持ちになっていたようです。その後、ドクターコースで執筆された博士論文が、その年の全米ベスト博士論文賞を受賞し、それを土台に、『イノベーションのジレンマ』が出版されることになったのです。
私は本当は役人を辞めるつもりはなかったのですが、役所というところはとてもジェネラリスト志向が強く、ある業務を1〜2年担当したら、別の部署に異動になることがほとんどです。そうして様々な部署を回りながら、仕事と経験の幅を広げていくのですが、私はもう少ししっかりとイノベーションを追求したくて、人事当局にお願いして筑波大に講師として出向させてもらったり、青木昌彦所長(当時)の面接をパスして経済産業研究所にフェローとして入れていただいたりする一方、東大先端研の社会人博士課程に入学し、児玉文雄教授(当時)の門をたたきました。先生の指導は厳しく、勤務時間外に博士論文を執筆するストレスで体重が優に10キロ以上減りました。全身が痩せたため、結婚指輪がユルユルになり、手を上に挙げると腕時計が肘まで下がってくる有様でした。そんなスパルタ指導のもとで、どうにか博士論文を完成させ、博士(学術)の学位をいただきました。
ちょうどその頃、関西学院がビジネススクールを開き、テクノロジーマネジメントを柱の一つにするということで、ご縁があって教鞭を執らせていただくことになりました。キャリア官僚というジェネラリストとして生きるより、大学教員としてイノベーションを一生の研究対象とし、それを学生さん達に伝えていく方が、私にとっては向いていて、且つ、よりやりたいことに思えたからです。それが2005年のことです。
大学の教員になって10年経ちました。以前『産学連携イノベーション』という、科学と技術の関係を定量的に測るという内容の、とても堅い本を書き、コアなマニアには売れているのですが、でも1,000部も出ていないんです。そこで、もう少し一般向けで、教科書にもなって、且つビジネスパーソンが電車の中で読めるようなもの、そういう本を書きたくて、約7年を費やし、昨秋いよいよ刊行となりました。それが、『日本のイノベーションのジレンマ ― 破壊的イノベーターになるための7つのステップ』という本です。初版は5,000部刷ったのですが、おかげさまで発売3日目には重版でき、2,000部を増刷し、今に至ります。

(2) イノベーションを通じて企業の競争力を高める
楠本: アメリカの大学院でイノベーションを学ばれ、そしてそれが先生の研究テーマとなったのですね。
玉田: そうです。イノベーションを通じて、日本に立地する企業の競争力をどうやって高めたら良いか、というのが生涯のテーマです。日本に立地する企業であれば、必ずしも日本(人)の資本でなければならない訳ではありません。日本に立地して、良い給料を払ってくれるのであれば、どこの国の企業でも構いません。資本は世界を自由に移動しますが、人は自宅の周辺にしか通えないし、引っ越しもそう簡単ではないので、自宅周辺に高いお給料を出してくれる会社が多く存在することがその国と国民にとってはとても大事です。
そのためには日本人がどうなるべきか、あるいは日本の経済がどうならなければいけないかといった産業政策にも興味があります。ただし、政策で出来ることには限りがあるとも同時に思っています。一番大事なことは、日本のビジネスパーソンの皆さんが正しい経営の理論と知識を身に付けられること。日本の常識が実は世界の非常識みたいなことが結構沢山あるので、日本の皆さんにも、少なくとも世界のビジネスパーソンと同じ水準の知識を身に付けてほしい。今回の本を著させていただいたのもその一環で、ぜひ多くの方に読んでいただければと思っています。
楠本: 日本と他の国々で、イノベーションを実現しようという時に決定的に異なっている点はどこでしょうか?
玉田: 日本と諸外国という切り分けよりは、おそらくアメリカ・イギリス系のアングロサクソン的経営なのか、ドイツ・日本的経営なのかで、コーポレートガバナンスや雇用環境がかなり異なります。そうすると、そういった“制度”、これはいわゆる法律などだけではなく人々が心の中で持っている常識や文化といったものも含む広い概念ですが、その“制度”が異なると、経済主体の動きが異なってきます。
例えばアメリカ、特にカリフォルニア州は雇用の流動性も高く、同業他社への転職も頻繁なため知識が流動し、且つジョブマーケットもオープンなので、実践的な高いスキルを持った人の給料は高い、という極めて明快な図式が成り立っています。それは、人や企業の新しい機会に対するチャレンジを促し、既存の考え方ではできないようなことをたくさん生み出す企業風土を作ります。そういう意味では、アングロサクソン型のコーポレートガバナンスの方が、より破壊的なイノベーションを起こしやすいということが言えるのではないかと思います。
一方日本は、一つの会社での勤続年数が比較的長く、既存のビジネスの延長線上で物事を考えがちという傾向がありますね。且つそういうビジネスプランを通すように、社内のフィルターがセットされているので、そういうところで破壊的ビジネスモデルを通そうとしてもなかなか難しい。かと言って、その日本でたくさんスピンアウト・ベンチャーが生まれているかというと、ここ10年ぐらいで少し雰囲気が変わってきたなという気はするものの、まだまだという感じですね。
日本企業は既存顧客によりよい製品、すなわちより性能が高く機能が豊富な持続的イノベーションの製品を作ることは得意としています。より燃費の良い車とか、より湿度や与圧が高く保て、窓が大きい快適な飛行機、解像度の高いデジカメなど、性能の高い製品を作るのは得意なのですが、それが行き過ぎると、顧客の「これで十分」という線を超えてしまうことがあるんですね。その時、超えたことに気付けない会社と、超えてしまったことに気付き、「この性能指標は十分だから、別の性能指標を立ててこっちで頑張ろう」と競争軸を変えられる会社に分かれるわけです。その分かれ目が会社の存続を左右するといっても過言ではない。性能の高い製品が必ずしも顧客に受け入れられるわけではありません。顧客がどの性能についてはどこまで求めているのかという視点を常に忘れないことが大切です。
>第2回に続く